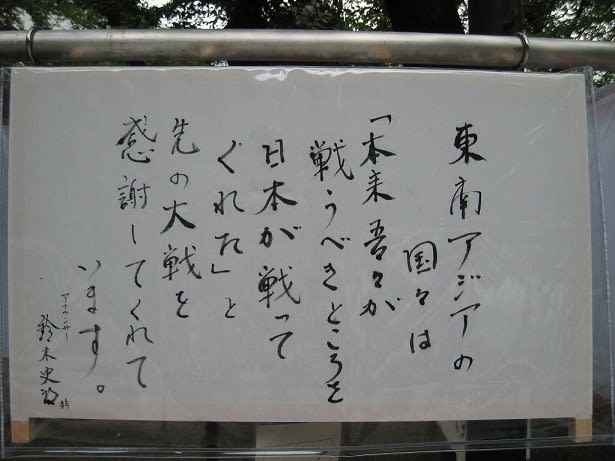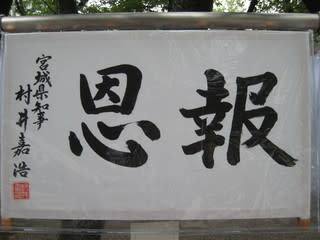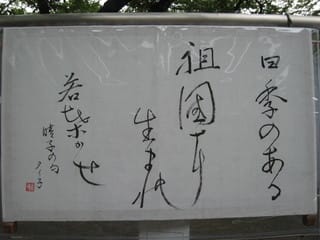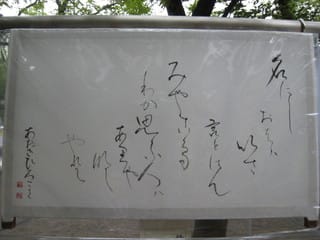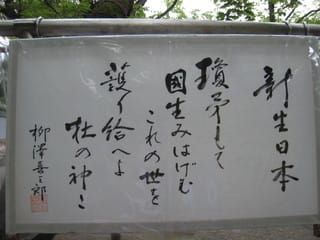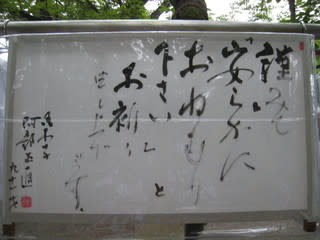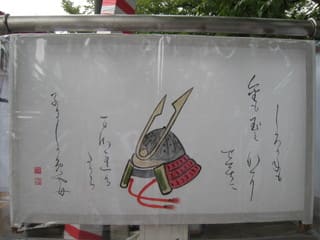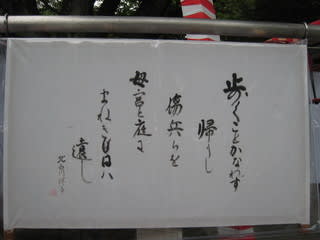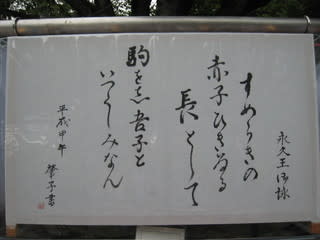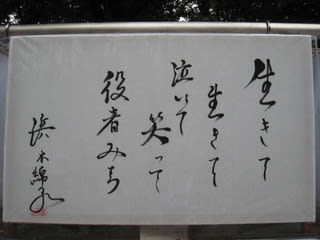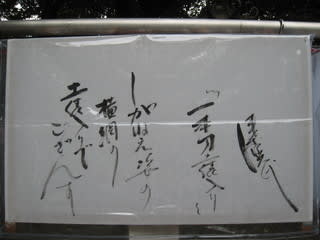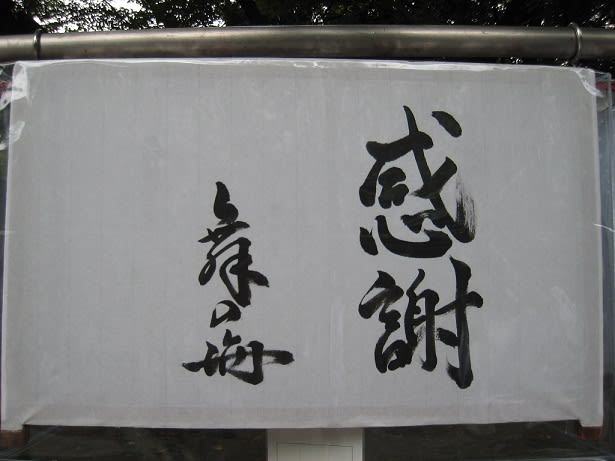今回ご紹介するのは「6TEEN」(著:石田衣良)です。
-----内容-----
『4TEEN』続編ついに刊行!
ぎこちない恋。初めての裏切り。
そして、少しだけリアルさを増してきた未来…。
超高層マンションを見上げる月島の路地で、ぼくたちはこの世界の仕組みを考える。
ダイ、ジュン、ナオト、テツロー ―永遠の青春小説。
-----感想-----
「4TEEN」の続編となります。
「6TEEN」は「4TEEN」の2年後が舞台で、ダイ、ジュン、ナオト、テツローの4人は高校一年生になりました。
今作も東京の月島を舞台に、4人の青春物語が展開されます。
今作も語りはテツロー。
4人の中では最も「普通」な少年です。
物語は以下の10編で構成されています。
おばけ長屋のおばあ
クラインの妖精
ユウナの憂鬱
携帯小説家に出会ったら
メトロガール
ウォーク・イン・ザ・プール
秋の日のベンチ
黒髪の魔女
スイート・セクシー・シックスティーン
16歳の別れ
どの章も最初に意味深な語りがあって、その章で起こることが漠然と示されます。
そして本編に入っていきます。
この構成は「池袋ウエストゲートパーク」のシリーズと同じです。
月島はもんじゃ焼きが有名で、この小説にもよく出てきます。
その中で、「もんじゃ焼きは漢字だと文字焼きと書く」というのは今まで意識したことがなく、新鮮でした。
お金がない時は具が何も入っていない「素もんじゃ」で、文字焼きの名のとおり鉄板に自分たちの名前や好きなアイドルの名前を書いたりして遊びながら食べているとのことです。
ちなみに4人がよく頼むもんじゃ焼きは「明太子もちチーズ」と「カレーコーンのベビースターラーメン入り」で、何度も登場しているのを読んでいたら私も特に「明太子もちチーズ」のほうを食べてみたくなりました![]()
4人は高校生になり、それぞれ別々の道へと進んでいきました。
テツロー(北川哲郎)は隣町の新富町にある新富高校という都立高校へ。
ジュン(内藤潤)は開城学院という東京で一番の進学校へ。
ナオト(岸田直人)は聖ヨハネ高校という私立のお坊ちゃん学校へ。
ダイ(小野大輔)は早朝から昼ごろまで築地の場外市場にある海産物問屋で働き、昼間は帰って仮眠して、夜はテツローと同じ高校の定時制に行っています。
ナオトはウェルナー症候群(早老症)という病気にかかっていて、普通の人の2倍も3倍も早く年をとってしまいます。
「6TEEN」の今作では一段と白髪が増えていました。
体も疲れやすいため、あまり負担をかけないようにストレートで大学まで行ける私立高校に入ったのでした。
ダイは前作で家族と自分の身に色々なことがあり、昼間は働き、夜は定時制高校に行くという道に進みました。
高校は別々になってもやはりこの4人組は仲良しで、よく一緒に集まっています。
「携帯小説家に出会ったら」では、携帯小説についてのテツローの語りが印象的でした。
「ぼくは携帯小説を読んだことがなかった。なんだか、あのちいさな液晶ディスプレイではメールの文章を読むくらいで十分な気がしていたのだ」
とありました。
私もテツローと同じく、あまり携帯小説を読む気にはならないです。
ただし、高校生の頃は”ファッション”を大事にするので、本の小説を読むのは周りから浮いている気がして避けるかも知れず、何となくお手軽で格好良さげな携帯小説を読むのはあるかも知れない、と思いました。
新富町、月島、佃(つくだ)、八丁堀、新川、箱崎町。このあたりの街は、みな細かな運河で結ばれている。
すごく興味を惹く一文でした。
運河で結ばれているこの辺りの街、一度じっくり散策してみたいです![]()
「さて、どうする。月島はとなりだけど、地下鉄にもどる?」
「こんな天気がいいのに、ひと駅分くらいで地下になんか潜れるかよ。歩いて、帰ろうぜ」
これはよく分かります。
私も天気が良い日はたくさん散歩したくなることがありますし^^
月島はもんじゃ焼きで、神保町は本屋。東京は街がものすごく専門化しているから、おもしろい。
これも良いなと思った一文です。
たしかに楽器の街の御茶ノ水などもありますし、専門化している街がありますね。
神保町には何度も足を運んでいるので分かりますが、完全に「本の街」となっています。
「黒髪の魔女」に出てきた以下の言葉も印象に残りました。
ついてないことや悪い運命は、ただ忘れちゃうのが一番いいのだ。いつまでも覚えていて、傷ついているよりはね。それは確かなことである。
私はわりと引きずりやすいタイプなので、いつまでもあれこれ考えて悩むより気にしないようにするのは大事なことだと感じています。
辛いことがあった時、落ち込んでしまうのは仕方ないとして、大事なのはその後いかに気持ちを立て直すかです。
考えても詮無きことは考えないようにして、忘れてしまえればそれが一番良いです。
作品全体を通してよく出てくるキーワードは隅田川、佃大橋、月島、もんじゃ焼きなど。
この作品を読んでいると私も隅田川沿いを歩いてみたくなりますし、佃大橋を歩いてみたくなりますし、月島のもんじゃ焼き屋にも行ってみたくなります。
昔ながらの下町の雰囲気のある街はやはり面白いなと思います![]()
※前回書いた「6TEEN」のレビューをご覧になる方はこちらをどうぞ。
※図書レビュー館を見る方はこちらをどうぞ。
※図書ランキングはこちらをどうぞ。
-----内容-----
『4TEEN』続編ついに刊行!
ぎこちない恋。初めての裏切り。
そして、少しだけリアルさを増してきた未来…。
超高層マンションを見上げる月島の路地で、ぼくたちはこの世界の仕組みを考える。
ダイ、ジュン、ナオト、テツロー ―永遠の青春小説。
-----感想-----
「4TEEN」の続編となります。
「6TEEN」は「4TEEN」の2年後が舞台で、ダイ、ジュン、ナオト、テツローの4人は高校一年生になりました。
今作も東京の月島を舞台に、4人の青春物語が展開されます。
今作も語りはテツロー。
4人の中では最も「普通」な少年です。
物語は以下の10編で構成されています。
おばけ長屋のおばあ
クラインの妖精
ユウナの憂鬱
携帯小説家に出会ったら
メトロガール
ウォーク・イン・ザ・プール
秋の日のベンチ
黒髪の魔女
スイート・セクシー・シックスティーン
16歳の別れ
どの章も最初に意味深な語りがあって、その章で起こることが漠然と示されます。
そして本編に入っていきます。
この構成は「池袋ウエストゲートパーク」のシリーズと同じです。
月島はもんじゃ焼きが有名で、この小説にもよく出てきます。
その中で、「もんじゃ焼きは漢字だと文字焼きと書く」というのは今まで意識したことがなく、新鮮でした。
お金がない時は具が何も入っていない「素もんじゃ」で、文字焼きの名のとおり鉄板に自分たちの名前や好きなアイドルの名前を書いたりして遊びながら食べているとのことです。
ちなみに4人がよく頼むもんじゃ焼きは「明太子もちチーズ」と「カレーコーンのベビースターラーメン入り」で、何度も登場しているのを読んでいたら私も特に「明太子もちチーズ」のほうを食べてみたくなりました

4人は高校生になり、それぞれ別々の道へと進んでいきました。
テツロー(北川哲郎)は隣町の新富町にある新富高校という都立高校へ。
ジュン(内藤潤)は開城学院という東京で一番の進学校へ。
ナオト(岸田直人)は聖ヨハネ高校という私立のお坊ちゃん学校へ。
ダイ(小野大輔)は早朝から昼ごろまで築地の場外市場にある海産物問屋で働き、昼間は帰って仮眠して、夜はテツローと同じ高校の定時制に行っています。
ナオトはウェルナー症候群(早老症)という病気にかかっていて、普通の人の2倍も3倍も早く年をとってしまいます。
「6TEEN」の今作では一段と白髪が増えていました。
体も疲れやすいため、あまり負担をかけないようにストレートで大学まで行ける私立高校に入ったのでした。
ダイは前作で家族と自分の身に色々なことがあり、昼間は働き、夜は定時制高校に行くという道に進みました。
高校は別々になってもやはりこの4人組は仲良しで、よく一緒に集まっています。
「携帯小説家に出会ったら」では、携帯小説についてのテツローの語りが印象的でした。
「ぼくは携帯小説を読んだことがなかった。なんだか、あのちいさな液晶ディスプレイではメールの文章を読むくらいで十分な気がしていたのだ」
とありました。
私もテツローと同じく、あまり携帯小説を読む気にはならないです。
ただし、高校生の頃は”ファッション”を大事にするので、本の小説を読むのは周りから浮いている気がして避けるかも知れず、何となくお手軽で格好良さげな携帯小説を読むのはあるかも知れない、と思いました。
新富町、月島、佃(つくだ)、八丁堀、新川、箱崎町。このあたりの街は、みな細かな運河で結ばれている。
すごく興味を惹く一文でした。
運河で結ばれているこの辺りの街、一度じっくり散策してみたいです

「さて、どうする。月島はとなりだけど、地下鉄にもどる?」
「こんな天気がいいのに、ひと駅分くらいで地下になんか潜れるかよ。歩いて、帰ろうぜ」
これはよく分かります。
私も天気が良い日はたくさん散歩したくなることがありますし^^
月島はもんじゃ焼きで、神保町は本屋。東京は街がものすごく専門化しているから、おもしろい。
これも良いなと思った一文です。
たしかに楽器の街の御茶ノ水などもありますし、専門化している街がありますね。
神保町には何度も足を運んでいるので分かりますが、完全に「本の街」となっています。
「黒髪の魔女」に出てきた以下の言葉も印象に残りました。
ついてないことや悪い運命は、ただ忘れちゃうのが一番いいのだ。いつまでも覚えていて、傷ついているよりはね。それは確かなことである。
私はわりと引きずりやすいタイプなので、いつまでもあれこれ考えて悩むより気にしないようにするのは大事なことだと感じています。
辛いことがあった時、落ち込んでしまうのは仕方ないとして、大事なのはその後いかに気持ちを立て直すかです。
考えても詮無きことは考えないようにして、忘れてしまえればそれが一番良いです。
作品全体を通してよく出てくるキーワードは隅田川、佃大橋、月島、もんじゃ焼きなど。
この作品を読んでいると私も隅田川沿いを歩いてみたくなりますし、佃大橋を歩いてみたくなりますし、月島のもんじゃ焼き屋にも行ってみたくなります。
昔ながらの下町の雰囲気のある街はやはり面白いなと思います

※前回書いた「6TEEN」のレビューをご覧になる方はこちらをどうぞ。
※図書レビュー館を見る方はこちらをどうぞ。
※図書ランキングはこちらをどうぞ。